こんにちは!
最近、簿記3級の勉強を始めました。
まず最初につまずいたのが、「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」という言葉。
左右に分かれてるのはなんとなく分かるけど、何が借りで何が貸しなのか、頭がこんがらがりますよね…。
今回は、自分なりに理解を深めていったポイントをまとめてみました!
借方・貸方の基本は「増える・減る」で覚える
各勘定科目には、「借方で増える」「貸方で増える」のルールがあります。
| 勘定科目の種類 | 借方(左)で増える | 貸方(右)で増える |
|---|---|---|
| 資産 | ✅ 増える | ❌ 減る |
| 負債 | ❌ 減る | ✅ 増える |
| 純資産(資本) | ❌ 減る | ✅ 増える |
| 収益 | ❌ 減る | ✅ 増える |
| 費用 | ✅ 増える | ❌ 減る |
このパターンを覚えておくと、仕訳の組み立てがスムーズになります!
家計の感覚で考えるとわかりやすい!
たとえば、「財布から現金を出してお弁当を買った」という場面。
- 現金が減る → 資産が減少 → 貸方(右)
- 食費(費用)が発生 → 費用が増加 → 借方(左)
仕訳にすると、
食費(借方)/現金(貸方)
といった形になります。
つまり、「左=増えるもの」「右=減るもの」と覚えるのではなく、何が増えて、何が減ったかを判断して左右に仕訳することが重要です。
クレアール流!ひらがなの向きで覚えると忘れにくい
私が受講しているクレアールの講義で紹介されていた、とても面白い覚え方があります。
それが、「ひらがなの書き順」に着目した方法です!
- 「かり」の「り」:左払い → 借方(左)
- 「かし」の「し」:右払い → 貸方(右)
つまり、文字の払いの方向=仕訳の方向と一致しているんです。
視覚的にイメージできるので、とても記憶に残りやすいですよ。
結論:借方・貸方は「慣れ」がいちばんの近道!
言葉の意味を覚えるよりも、「何が増えた・減った?」を考えながら仕訳を書いていくと、だんだん慣れていきます。
| ポイントまとめ |
|---|
| 左右で位置を固定して覚える |
| 勘定科目ごとのルールを整理して暗記 |
| 自分の生活に当てはめてイメージ化 |
| 書き順(ひらがな)の向きで覚えると視覚で定着 |
少しずつ、「簿記の世界の言語」に慣れていきましょう!
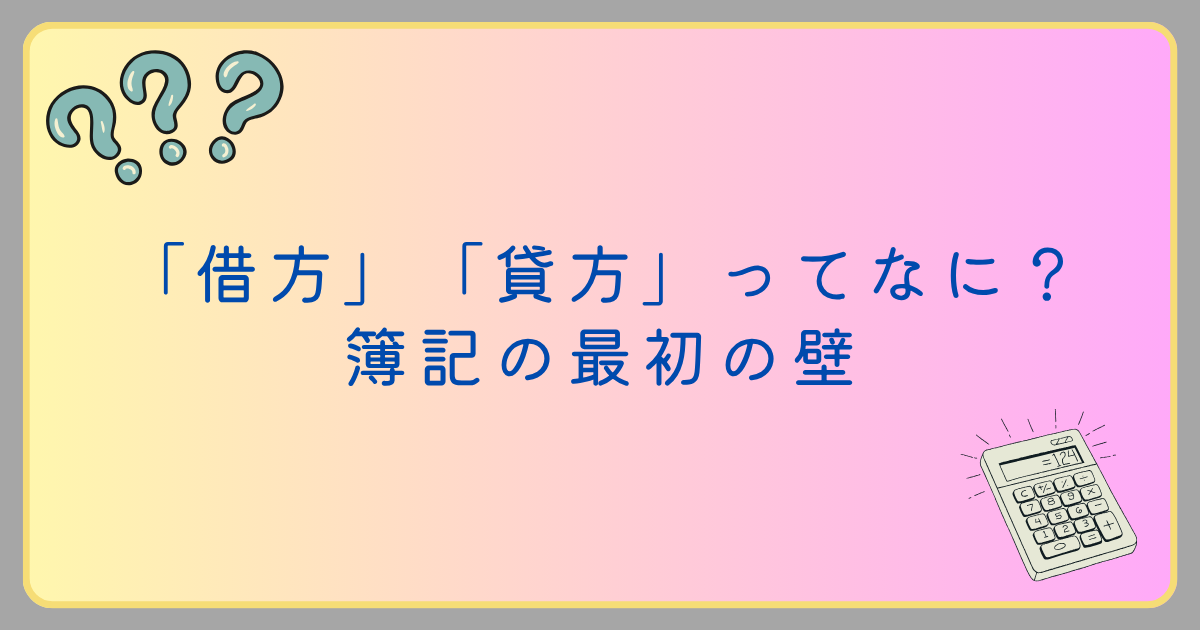
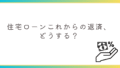
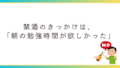
コメント